この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
子育てにいいという情報がありすぎて、どんどん足して「あれもこれも」「それも」「これもできなきゃ」とたくさんの情報を得ようとしていく私、それを実践しようとする私。
そんな、子育てに関する情報の多さに溺れそうになっていた私に【待った!!】をかけてくれたそんな一冊の本に出会いました。
かわいい我が子。苦労せずつらい思いをせず大人になってほしい。そんな気持ちから、巷で言われている良いものをたくさん詰め込んでしまっている。
でもこれって本当にうちの子に合ってる?とジレンマを抱えている方にぜひ読んでいただきたい本を紹介していきます。
子育てに悩んでいた私が手に取った本
子育てのアドバイスや、子育て情報って世の中にあふれかえっていますよね。
小さい頃からの知育が重要とか、モンテッソーリ教育・シュタイナー教育とか、習い事は?受験はどうする?などなど。知らないことがあると不安になるし、周りと比べてうちの子は大丈夫かしらと勝手に心配になる。
アルゴリズムの関係からか、一時期の私のInstagramでは知育関連の情報がずらりと並んでいて、それを追えない自分が不甲斐ないと感じたことも。

こどもたちになにもできていないんじゃないかという不安から、子育てが楽しいと思えないなんていう時期がありました。
「ちゃんと育てなきゃ」が苦しかった
Instagramでは、素敵なママ達が子どもたちにたくさんの体験をさせている姿をよく見かけます。
私もそうなりたい。と思う気持ちもあるし、私がちゃんと育てなきゃうちの子たちはどうなってしまうの?という「ちゃんと育てなきゃ」が無意識のうちにプレッシャーになっていたと思います。
そんな中、本屋さんでふと目に入ったのが『引き算の子育て』という本でした。
「これをするといいよ」「あれをするといいよ」という足し算の情報ではなく「これもいらない」「あれもいらない」と仕分けする【引き算の発想】
子どものことをよく見て、子どものありのままをおもしろがる子育ての重要性に気が付きました。
『引き算の子育て』はどんな本?
2名のカリスマ教育者と教育ジャーナリストの3名の鼎談本。
宮本算数教室の主宰・宮本哲也さん、
私塾「いもいも」主宰・井本陽久さん、
そして教育ジャーナリスト・おおたとしまささんの3名で鼎談されている本です。
読んで感じたこと・第一印象
とにかく面白い本でした。3人がお話されている本なので、とても読みやすくてサクサク読めます。
初っ端から、人生には「野人コース」「家畜コース」二通りしかないと。表現が面白くて、「そうだよなー」と、付箋を貼る手が止まりませんでした。
・親が先回りしてやることなんてない
・子どもをいじるな(子どもがやりたいようにやっているだから邪魔をするな)
心に刺さった言葉と気づき
井本 勉強もできてほしいし、スポーツや芸術もできてほしいし、お友達もちゃんといてほしいというのが親の欲求になっちゃってるんですよね。子どもは確実に親の欲求を察知するので、本当はお友達なんていなくても困らないのに、お友達をつくらないといけないと思って、苦しんでしまったりします。p172
宮本 この世の中に生きていれば、不安になることはいっぱいあるけれど、子どもに対しては「生まれてきてくれてありがとう!」。それだけです。あれができない、これができない、どうでもいいじゃん、そんなの。p178

ほんとそうだよね。
自分が「やりすぎていた」ことに気づく
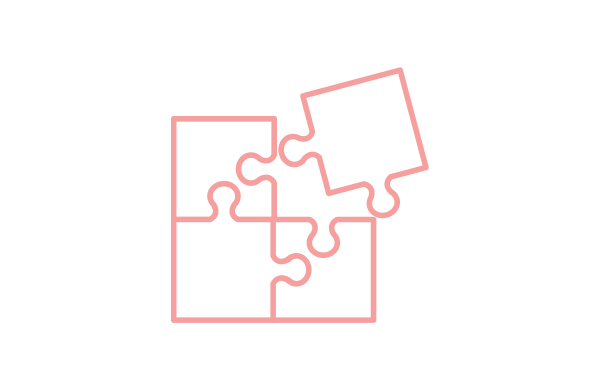
この本を読んで、私は自分の子育てを振り返ってみました。確かに、私も知らず知らずのうちに「やりすぎ」ていたことがたくさんありました。
例えば、子どもが自分でやろうとしていることに手を出し過ぎていたこと。「もっと上手になってほしい」「もっと早くできるようになってほしい」という私の願望が、子どもの成長のペースを尊重することを忘れさせていたのです。
また、SNSで見る「理想の子育て」に惑わされ、我が子の個性や興味関心よりも、世間的に評価されそうなことに価値を置いていました。子どもが本当に興味を持っていることより、「これをやっておけば将来役立つかも」という不安からの選択をしていたことに気づきました。
子どもを信じるってこういうことかも
本書を通じて、「子どもを信じる」とは何かについても考えさせられました。それは単に「子どもは何でもできる」と過大な期待をすることではなく、子どもの「今」を尊重し、子どものペースで成長することを受け入れること。その子なりの学び方、考え方、成長の仕方があることを認めることなのだと思います。
子どもが自分でやりたいことに夢中になっている姿を見守る。それがうまくいかなくても、すぐに手を貸さず、子ども自身が解決策を見つける機会を奪わない。それが「信じる」ということなのかもしれません。
私が実践してみた”引き算の子育て”

口を出しすぎない工夫
本書を読んだ後、まず私が実践したのは「口を出しすぎない」ことでした。子どもが自分でやろうとしていることには、見守る姿勢を意識しました。例えば、朝の支度。以前は「早くしなさい」「そんなやり方じゃダメでしょ」と口やかましく言っていましたが、今は子どもが自分のペースで進めることを尊重しています。
もちろん、時間の制約はありますが、それも「何時までに出かける必要があるよ」と伝えるだけにして、あとは子ども自身が考えて行動できるよう見守るようにしました。すると、少しずつですが子どもが自分で考えて行動するようになってきたのです。
また、子どもの遊びや創作活動にも余計な指示を出さないよう心がけています。「こうした方がいいよ」「それはそうじゃなくて」という言葉を飲み込み、子どもが自分なりに考えて作り上げる過程を大切にしています。
見守ることの難しさと変化
正直に言うと、見守ることは想像以上に難しいものでした。子どもがうまくできないとき、失敗しそうなとき、つい手を出したくなります。でも、グッと我慢して見守ることで、子どもは試行錯誤し、時には失敗しながらも、自分の力で解決する力を少しずつ身につけていきました。
最初は時間がかかることもありましたが、徐々に子どもが自分で考え、自分で判断する場面が増えてきました。そして何より、子どもが「自分でできた!」と嬉しそうに報告してくれる瞬間が、以前より格段に増えたのです。
また、私自身も変わりました。子どもの行動を細かく管理したり、あれこれ指示を出したりする必要がなくなり、精神的にずっとラクになりました。子どもを見る目も変わり、「できないところ」ではなく「今、夢中になっていること」「自分なりに工夫していること」に目が向くようになったのです。
この本をおすすめしたいママたち
– つい口を出してしまう
– 子どもとぶつかる毎日に悩んでいる
– 「もっとラクに子育てしたい」と思っている
特に、子育ての情報に振り回されている方、SNSの理想の子育てに追いつけない自分に落ち込んでいる方、子どもの「できない」ことばかりに目が行ってしまう方には、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

この本は、子育てを「減らす」ことで見えてくる大切なものについて教えてくれます。子どもを信じ、見守ることの大切さ。そして、そうすることで親自身もラクになれることを。
まとめ:子育ては引き算が大切。足しすぎ注意。
『引き算の子育て』を読んで、私は気づきました。子育てって、たくさんの情報を詰め込む「足し算」ではなく、余計なものを削ぎ落としていく「引き算」でいいんだと。
子どもに必要なのは、あれもこれもと与えることではなく、子どもの「今」を大切にし、子どものペースを尊重すること。そして親が子どもに伝えるべきことは、「生まれてきてくれてありがとう」という気持ちだけなのかもしれません。
この本のおかげで、私の子育ては確実に楽になりました。そして何より、子どもとの関係がより豊かになったと感じています。「ちゃんとしなきゃ」という思いに縛られていた子育てから解放され、子どもの姿をありのままに見ることができるようになった今、子育ては前より楽しくなりました。
もし、あなたも子育てに疲れを感じているなら、ぜひこの『引き算の子育て』を手に取ってみてください。子育ての新しい視点が開けるかもしれません。

おおたとしまささんの新刊。『子どもの体験 学びと格差』もとても面白かったですよ。


